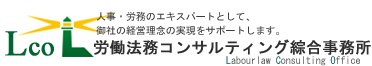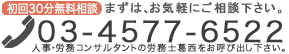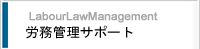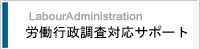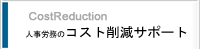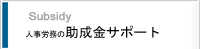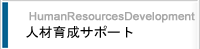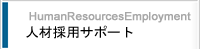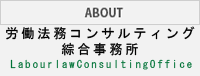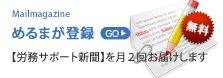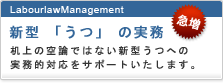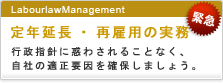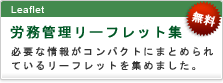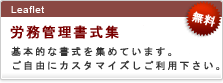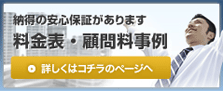| ‚¤‚آ•a“™‚جگ¸گ_ژ¾ٹ³‚ةœëٹ³‚µ‚½•ٌچگ‚ھ‚ ‚ھ‚ء‚ؤ‚«‚½‚ئ‚«‚ةپAگlژ–کJ–±•”–ه‚ھ‚ـ‚¸ٹm”F‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢‚ج‚ح‹ئ–±‹Nˆِگ«‚ج—L–³پB‹ئ–±‹Nˆِگ«‚ج”»’f‚·‚éکJ“ٹîڈ€ٹؤ“آڈگ‚ج”»’f‚ج‹’‚èڈٹ‚ئ‚ب‚é’ت’BپEژwگj‚âکJچذ”F’è—¦‚ًŒ©‚ؤ‚ف‚é‚ئپA‹ئ–±‹Nˆِگ«‚ح”F‚ك‚ç‚ê‚ة‚‚¢ŒXŒü‚ة‚ ‚é‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚و‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤پB |
 |
گ¸گ_ژ¾ٹ³‚ج‹ئ–±‹Nˆِگ«‚ج”»’fٹîڈ€‚ة‚آ‚¢‚ؤ |
| گS—“I•‰‰×‚ة‚و‚éگ¸گ_ڈلٹQ‚جکJچذگ\گ؟‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA•½گ¬‚P‚P”N‚XŒژ‚P‚S“ْ•t’ت’BپuگS—“I•‰‰×‚ة‚و‚éگ¸گ_ڈلٹQ“™‚ةŒW‚é‹ئ–±ڈêٹO‚ج”»’fژwگj‚آ‚¢‚ؤپv‚ةٹî‚أ‚«‹ئ–±‹Nˆِگ«‚ج”»’f‚ھچs‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½‚ھپA•½گ¬‚Q‚R”N‚P‚QŒژ‚Q‚U“ْ’ت’B‚إگV‚½‚ةپuگS—“I•‰‰×‚ة‚و‚éگ¸گ_ڈلٹQ‚ج”F’èٹîڈ€‚ة‚آ‚¢‚ؤپv‚ھŒِ•\‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB•½گ¬‚Q‚R”N‚P‚QŒژ‚Q‚U“ْ’ت’B‚حپAڈ]—ˆ‚©‚çکJ“ٹîڈ€ٹؤ“آڈگ‚ة‚¨‚¢‚ؤ—p‚¢‚ؤ‚¢‚½‹ئ–±‹Nˆِگ«‚ج”»’fٹîڈ€‚ً‰ü‚ك‚ؤ’ت’B‚ئ‚µ‚ؤ”‚µ‚½“à—e‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¨‚èپA‚ئ‚è‚ي‚¯”»’fٹîڈ€‚ھŒµٹi‰»‚³‚ꂽ‚ي‚¯‚إ‚àٹةکa‚³‚ꂽ‚ي‚¯‚إ‚à‚ب‚¢‚و‚¤‚إ‚·پB پuگS—“I•‰‰×‚ة‚و‚éگ¸گ_ڈلٹQ‚ج”F’èٹîڈ€‚ة‚آ‚¢‚ؤپv‚ة‚¨‚¢‚ؤپA’·ژٹشکJ“‚ھ‚ ‚éڈêچ‡‚ج•]‰؟•û–@‚ئ‚µ‚ؤپAپu160ژٹشپvپu120ژٹشپv‚ئ‚¢‚¤گ”ژڑ‚ھŒ©‚ç‚ê‚é‚و‚¤‚ةپA‹ئ–±‹Nˆِگ«‚ھ”F’肳‚ê‚é‚ة‚حپA‚©‚ب‚èچ‚‚¢ٹîڈ€‚ھگف’肳‚ê‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ھ‚ي‚©‚è‚ـ‚·پB |
|
 |
 |
گ¸گ_ژ¾ٹ³ٹضکA‚جگf’fڈ‘‚ھڈo‚ؤ‚«‚½‚ç‹ئ–±‹Nˆِگ«‚ج‰آ”\گ«‚ھ‚ ‚é‚©‚ا‚¤‚©‚ًŒںڈط‚·‚é |
| گ¸گ_ژ¾ٹ³ٹضکA‚جگf’fڈ‘‚ھڈo‚ؤ‚«‚½‚çپA‚ـ‚¸‚ح‹ئ–±‹Nˆِگ«‚ج‰آ”\گ«‚ھ‚ ‚é‚©‚ا‚¤‚©‚ًŒںڈط‚µ‚ـ‚·پB•½گ¬‚Q‚R”N‚P‚QŒژ‚Q‚U“ْ’ت’BپuگS—“I•‰‰×‚ة‚و‚éگ¸گ_ڈلٹQ‚ج”F’èٹîڈ€‚ة‚آ‚¢‚ؤپv‚ًژQچl‚ةپA”‹ة“x‚ج’·ژٹشکJ“””ڈo—ˆژ–‚ئ‚µ‚ؤ‚ج’·ژٹشکJ“”‚ج—L–³‚ة‚آ‚¢‚ؤٹm”F‚µ‚ـ‚·پB‹ئ–±‹Nˆِگ«‚ھ‚ظ‚عٹmژہ‚ةŒ©چ‚ـ‚ê‚邱‚ئ‚ھ‚ب‚¯‚ê‚خپAژ„ڈ•a‚ئ‚µ‚ؤ‘خ‰‚µ‚ـ‚·پB‚ـ‚½پA•½گ¬‚Q‚R”N‚P‚QŒژ‚Q‚U“ْ’ت’B‚إ‚حپAپu‡@”F’èٹîڈ€‚ج‘خڈغ‚ئ‚ب‚éگ¸گ_ڈلٹQ‚©‚ا‚¤‚©پv‚ة‚¨‚¢‚ؤپAICD-10‘و‡Xڈحپuگ¸گ_‹y‚رچs“®‚جڈلٹQپv•ھ—ق‚ً—p‚¢‹ئ–±‚ةٹضکA‚µ‚½”ڈا‚·‚é‰آ”\گ«‚ج‚ ‚éگ¸گ_ڈلٹQ‚ج‘م•\“I‚ب‚à‚ج‚حپA‚¤‚آ•aپiF3پj‚â‹}گ«ƒXƒgƒŒƒX”½‰پiF4پj‚ب‚ا‚ئ‚¢‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB“ء‚ةچًچ،ژو‚èڈم‚°‚ç‚ê‚邱‚ئ‚ج‘½‚¢ƒpپ[ƒ\ƒiƒٹƒeƒBپ[ڈلٹQپiF6پj‚حگ¶—ˆ“I‚بŒآگl‚جگ«ٹi‚ة‚و‚é‚à‚ج‚إ‹ئ–±‹Nˆِگ«‚ج‰آ”\گ«‚ھ‚ ‚é‚ئ‚ح‚¢‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚و‚¤‚إ‚·پB | |
 |

| •œگE‚ج‰آ”غ‚ًŒں“¢‚·‚éڈم‚إ‚àپAژهژ،ˆم‚âژY‹ئˆم‚©‚瓾‚½ڈî•ٌ‚ً—ک—p‚·‚éڈم‚إ‚àپA‰ïژذ‘¤‚ھ‹xگE‚ئ‚·‚éگ³‚µ‚¢——R‚ً’m‚èپA‹xگE‚ة“ü‚é’iٹK‚إگ³ٹm‚ة–{گl‚ة“`‚¦‚ؤ‚±‚‚ھ•K—v‚إ‚·پB‹xگE‚ج——R‚ًپu•a‹C‚¾‚©‚çپv‚ئ‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ئپA•œگEٹîڈ€پAٹîڈ€‚ض‚ج‚ ‚ؤ‚ح‚كپAˆمژt‚ئ‚ج‚â‚èژو‚èپA‚·‚ׂؤ‚ھƒYƒŒ‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚·پB |

| پu•œگE‚³‚¹‚é‚ׂ«‚©پv‚جچإڈI“I”»’f‚ح‰ïژذ‚ھچs‚¢‚ـ‚·‚ھپA‚»‚ج”»’fƒ|ƒCƒ“ƒg‚حˆسٹO‚ب‚ئ‚±‚ë‚ة‰B‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‘هگط‚ب‚±‚ئ‚حپAچإڈI”»’f‚ـ‚إ‚ة‚ا‚و‚¤‚و‚¤‚بˆسگ}‚ًژ‚ء‚ؤ‚ا‚ج‚و‚¤‚بƒvƒچƒZƒX‚ً“¥‚ق‚ج‚©گي—ھ“IƒXƒgپ[ƒٹپ[‚ً‚à‚ء‚ؤ‘خ‰‚·‚邱‚ئ‚إ‚·پB |
 |
•œگE‚جٹîڈ€‚حپuکJ–±’ٌ‹ں‚إ‚«‚éپv‚و‚¤‚ة‚ب‚邱‚ئ |
| کJ“Œ_–ٌڈم‚جکJ“ژز‚ج‹`–±‚حکJ–±’ٌ‹ں‚·‚邱‚ئ‚إ‚·پBکJ–±‚ج’ٌ‹ں‚حŒ —ک‚إ‚ح‚ب‚‹`–±‚إ‚·پBڈ]‚ء‚ؤپA•œگE‚جٹîڈ€‚حپuکJ–±’ٌ‹ں‚ھ‚إ‚«‚éپv‚±‚ئ‚ةگs‚«‚ـ‚·پB‚ا‚جگE–±‚ة‚آ‚¢‚ؤپuکJ–±’ٌ‹ں‚إ‚«‚éپv‚©‚حپAکJ“Œ_–ٌپi–ٌ‘©پj‚إ“–ٹYکJ“ژز‚ھ‹پ‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éگE–±‚ة‚آ‚¢‚إ‚·پB‚آ‚ـ‚èپAŒ»گEٹîڈ€‚ھ‘أ“–‚µ‚ـ‚·پB Œْگ¶کJ“ڈب”•\‚جپwگS‚جŒ’چN–â‘è‚ة‚و‚è‹x‹ئ‚µ‚½کJ“ژز‚جگEڈê•œ‹Aژx‰‡‚جژèˆّ‚«پxپi•½گ¬‚Q‚P”N‚RŒژ‰ü’ùپj‚ھپuپw‚ـ‚¸‚حŒ³‚جگEڈê‚ض‚ج•œ‹Aپx‚جŒ´‘¥پv‚ً‹‚گà‚ˆبڈمپA‹xگE‘O‚جŒ»ڈê‚ة–ك‚·‚±‚ئ‚ً‘O’ٌ‚ة”»’f‚µ‚ـ‚·پiŒ»گEٹîڈ€پjپBگEڈê—vˆِ‚ئŒآگl—vˆِ‚ج•s“Kچ‡‚ھگ¶‚¶‚ؤ‚¢‚éڈêچ‡‚إ‚ ‚ء‚ؤ‚àپA“¯ژèˆّ‚«‚ح”z’u“]ٹ·‚ًگد‹ة“I‚ةٹ©‚ك‚ؤ‚¢‚ـ‚¹‚ٌپB | |
 |
 |
•œگE”»’f‚·‚éچغ‚جژ‘—؟‚حکJ“ژز‘¤‚ة’ٌڈoگس”C‚ھ‚ ‚é |
| •œگE‰آ”غ”»’f‚حپA‰ًŒظ—P—\ٹْٹش–—¹‚ة”؛‚¢کJ“Œ_–ٌڈI—¹‚ئ‚¢‚¤Œّ‰ت‚ًگ¶‚¶‚³‚¹‚é‚©”غ‚©‚جکJ“Œ_–ٌڈم‚ج”»’f‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·پB‚»‚ج‚½‚كپAچإڈI”»’fŒ ژز‚ح“–‘R‰ïژذ‚ة‚ ‚è‚ـ‚·پB ‚±‚ج”»’f‚ة‚حپAچ‡—گ«‚ھ‹پ‚ك‚ç‚êپA”»’fژ‘—؟‚ھ•K—v‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·پB‚µ‚©‚µپA”»’fژ‘—؟‚ج’ٌڈoگس”C‚حکJ“ژز‚ة‚ ‚è‚ـ‚·پB‰ïژذ‚ة‹پ‚ك‚ç‚ê‚é‚ج‚ح”»’fژ‘—؟ژûڈW‚جپu“w—حپv‚ة‚ئ‚ا‚ـ‚è‚ـ‚·پB”»’fژ‘—؟‚حکJ“ژز‘¤‚ة‚ ‚é‚ج‚إپA‰ïژذ‚حکJ“ژز‚ةژ‘—؟’ٌڈo‚ً‹پ‚ك‚³‚¦‚·‚ê‚خ‘«‚è‚ـ‚·پB ‚ب‚¨پA‘OŒf‚جپwگS‚جŒ’چN–â‘è‚ة‚و‚è‹x‹ئ‚µ‚½کJ“ژز‚جگEڈê•œ‹Aژx‰‡‚جژèˆّ‚«پx‚إ‚حپAژهژ،ˆم‚ج”»’f‚ة‚آ‚¢‚ؤپAپu•aڈَ‚ج‰ٌ•œ’ِ“x‚ة‚و‚ء‚ؤگEڈê•œ‹A‚ج‰آ”\گ«‚ً”»’f‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ھ‘½‚پA‚»‚ê‚ح‚½‚¾‚؟‚¢گEڈê‚إ‹پ‚ك‚ç‚ê‚é‹ئ–±گ‹چs”\—ح‚ـ‚إ‰ٌ•œ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚©”غ‚©‚ج”»’f‚ئ‚حŒہ‚ç‚ب‚¢پv‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚ـ‚½پAپuکJ“ژز‚ج‰ئ‘°‚جٹَ–]‚ھٹـ‚ـ‚ê‚ؤ‚¢‚éڈêچ‡‚à‚ ‚éپv‚ئ‚à‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB ژهژ،ˆم‚جگf’fڈ‘‚ً–دگM‚·‚邱‚ئ‚ب‚پAکJ“’ٌ‹ں‚ًˆہ’è“I‚ة‘±‚¯‚ç‚ê‚é‚©پAژdژ–‚ً”C‚¹‚ç‚ê‚é‚©پAژüˆح‚جکJ“ژز‚ھ“–ٹYکJ“ژز‚ئˆêڈڈ‚ةژdژ–‚ھ‚إ‚«‚é‚ج‚©‚ئ‚¢‚¤ژ‹“_‚إپA“–ٹYٹé‹ئ‚ھ”»’f‚·‚ׂ«‚إ‚·پB |
|
 |